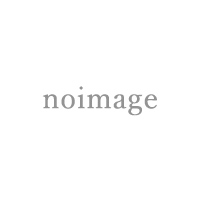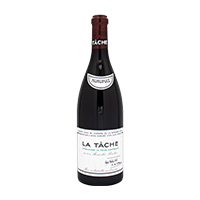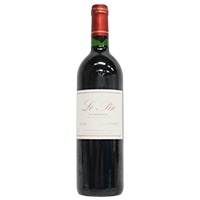ワインの買取
ワインを売るなら
お酒買取専門店ファイブニーズ
※ESP総研2022年9月調べ
- お酒買取のファイブニーズTOP
- ワインの買取
ワインの価格高騰中!
国内のワイン消費量は10年間で1.5倍に増えており、需要が高まっております。
代表的なワインとしてロマネコンティが取り上げられますが生産量を絞り込み、尚且つ手間のかかる農法・製法により作られる極上のワインです。世界中で高い人気を誇っているワインになり高値で取引されております。
そんな価値があるワインだからこそ、少しでも高く売りたい方は、お酒買取専門店であるファイブニーズにお任せください。
ワインを高く売るなら
 価格高騰中の
価格高騰中の
今が売り時です!

| 過去の買取価格 | 参考買取価格※ | ||
|---|---|---|---|
| DRCロマネコンティ2011 | 900,000円 | 234% |
2,100,000円 |
| DRCロマネコンティ2012 | 900,000円 | 234% |
2,100,000円 |
| DRCラ・ターシュ2010 | 180,000円 | 339% |
610,000円 |
| DRCモンラッシェ2011 | 300,000円 | 384% |
1,150,000円 |
※買取相場は日々変動しますので、実際の買取価格と相違がある場合がございます。 商品の状態が良くても製造年代、箱・ラベル・ボトルデザイン、保管状態、箱・替栓・シリアル・冊子など付属品の有無、相場状況により金額は変動します。 最新の価格情報についてはお気軽にお問合せ下さい。 本数が多い場合は出張でのお買取り対応も行っております。 出張先の地域と売却ご予定のお品物によってご対応できない場合がございます。ご希望の場合は一度お問合せください。
国内のワイン消費量は増えており、需要が高まっております。代表的なワインとしてロマネコンティが取り上げられますが生産量を絞り込み、尚且つ手間のかかる農法・製法により作られる極上のワインです。現在世界的にインフレ傾向になってきており、その影響を受けてワインの価格が上昇してきています。そのため、価格が高騰している今が売り時です!
完全無料!査定依頼はこちら
査定・キャンセル0円で
気軽にご相談ください
お客様の状況に合わせて、
3つの無料査定方法よりお選びいただけます。
その場で査定も可能!お電話でお気軽にお問い合わせください。
ネットからのご相談・査定依頼はこちら
ネットで完結!24時間以内に査定結果をお伝えいたします。
お酒のプロが丁寧に査定いたします

ファイブニーズはお酒の専門家、ソムリエやSAKE DIPLOMAと言ったお酒の有資格者が在籍するお酒の買取専門店です。
累計120万本以上を買取してきたプロのスタッフの目でお客様の大事なお酒を丁寧に査定いたします。
「譲り受けたけど価値がよく分からない」「お酒の名前が読めない」と言ったお悩みでもお気軽にご相談ください。
ご安心してファイブニーズにお任せください。
全国どこでも対応可能!
選べる3つの買取方法
※各買取方法の詳細はリンク先をご確認ください。
ファイブニーズは
全国15店舗展開中!
その場ですぐ現金化!
お店をお探しの方はこちら
-
- 北海道
- 北海道札幌店
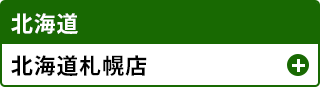
-
- 東 北
- 宮城仙台店

-
- 関 東
- 錦糸町本店

-
- 関 東
- 新宿歌舞伎町店
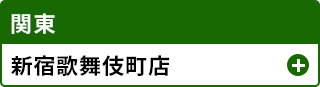
-
- 関 東
- 六本木店

-
- 関 東
- 埼玉大宮店

-
- 関 東
- 神奈川横浜店
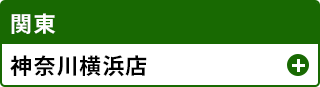
-
- 関 東
- 千葉店

-
- 中 部
- 愛知名古屋店
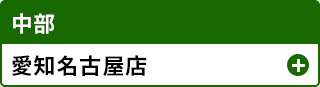
-
- 関 西
- 大阪心斎橋店
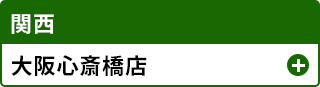
-
- 関 西
- 兵庫神戸店

-
- 関 西
- 京都店

-
- 中 国
- 広島店

-
- 九 州
- 福岡博多店

-
- 九 州
- 熊本店

お近くに店舗がない地域でも
出張買取、宅配買取で全国どこでも対応します!
店舗及び出張買取スタッフにて
コロナ対策を行っております
-

スタッフ体温管理
毎日検温を行いスタッフの体調管理
-

店内消毒清掃
人が良く触る部分なども細かく消毒清掃
-

手洗い消毒
こまめな手洗いとアルコール消毒
-

飛沫防止
対応カウンターに飛沫防止パーテーションの設置
人気ワイン銘柄一覧
ワイン・ワイン買取に関する
お役立ち情報
ファイブニーズが選ばれる3つの理由

-
1お酒買取日本一!※
年間買取額40億円突破!
業界No.1の安心と信頼
※ESP総研2022年9月調べ -
2お酒のプロが在籍
お酒のプロが在籍する事で、
コレクターも納得の高額査定を実現 -
3豊富な販路による高価買取
ヤフオクベストアワード、
楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーなど
多数の受賞実績あり
買取価格表(参考)
※買取相場は日々変動しますので、実際の買取価格と相違がある場合がございます。 商品の状態が良くても製造年代、箱・ラベル・ボトルデザイン、保管状態、箱・替栓・シリアル・冊子など付属品の有無、相場状況により金額は変動します。 最新の価格情報についてはお気軽にお問合せ下さい。 本数が多い場合は出張でのお買取り対応も行っております。 出張先の地域と売却ご予定のお品物によってご対応できない場合がございます。ご希望の場合は一度お問合せください。