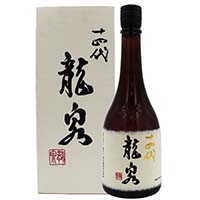日本酒の賞味期限ってどのくらい?時間が経っても飲める理由を解説!
古い日本酒であっても未開封であれば菌は繁殖しにくく、飲むことができます。しかし、保管状況によっては風味が劣化しやすいため注意が必要です。
本記事では、日本酒の賞味期限がない理由や保管方法、古くなった日本酒の確認の仕方、利用方法などについて解説します。
目次
日本酒には賞味期限表示がない
古い日本酒の賞味期限を確認したとき、製造年月しか書かれていないケースがあり、見た目だけでは腐っているかどうかの判断が難しいこともあるでしょう。加工食品など、スーパーで販売される食べ物や飲み物の多くは、食品衛生法の規定により消費期限か賞味期限の表示が義務付けられていますが、日本酒に関しては、消費期限・賞味期限の表示を省略して問題ないと定められています。(※)
日本酒は、基本的に高濃度のアルコールの殺菌作用により腐敗の恐れがなく、長期間の保存が可能であると判断されるためです。同様の理屈から、焼酎やワイン、ウイスキーなどのアルコール度数の高いお酒も賞味期限は書かれていません。
ただし、お酒の中でもビールや缶酎ハイなどには賞味期限が定められているため、早めに飲むようにしましょう。
※参考:独立行政法人 国民生活センター.「清酒に賞味期限が表示されていない」
日本酒ラベルの日付は「賞味期限ではなく、製造年月」
日本酒のラベルには賞味期限は書かれていないものの、製造年月は記載されています。これは、製造時期の明記が酒税法により必要記載事項として定められていたためです。しかし、2023年1月に酒税法が改正されてからは、製造年月の記載は任意記載事項となりました。(※)そのため今後発売される日本酒には、ラベルに何の日付も記載されないものが出てくるかもしれません。
なお、日本酒の製造年月は絞ったり濾過したりした日ではなく、瓶詰された時期を指します。
※参考:国税庁.「「清酒の製法品質表示基準」の概要」
通常の日本酒は製造年月から1年ほど
日本酒は賞味期限がなく腐りにくいとはいえ、10年、20年先もおいしく飲めるとは限りません。一般的に本醸造酒などの普通の日本酒がおいしく飲めるのは、製造から1年程度とされ、時間が経てば製造元が想定していた味わいとはかけ離れてしまうこともあります。生貯蔵酒の場合は約9カ月
本醸造酒以外の日本酒はどうかといえば、生貯蔵酒・吟醸酒・純米酒・生酒、ともに9カ月程度がおいしく飲める目安です。火入れ回数が少なかったり繊細な香りを活かしたりしている日本酒は、未開封であってもできるだけ早めに飲んだ方がよいでしょう。なお、上記はあくまでも目安のため、保存状況によってはさらに風味の劣化が早まる可能性もあります。
日本酒は腐らないって本当?
日本酒は未開封であれば腐る恐れはほとんどないと考えられており、消費期限や賞味期限の表示は義務付けられていません。消費期限や賞味期限は、食中毒など、衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生法に基づいて定められているものです。(※)ただし、火入れしていない日本酒では、稀に乳酸菌の一種である火落菌(ひおちきん)が増殖することがあります。
火落菌はアルコール度数15%以上でも生育でき、増殖すると白濁して味も酢のようになり著しく劣化するため、一見腐ったように見えるのが特徴です。
雑菌ではないので間違って飲んでしまっても人体に影響はありませんが、火落菌が増殖した日本酒は飲まずに破棄しましょう。
※参考:内閣府.「○食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令」
開封後はできるだけ早めに飲むのが理想
日本酒を長期保存できるのは未開封のときに限られており、開封後は変質が進むのでできれば1週間程度で飲み切るのが理想です。開封後は瓶口を清潔にして、直射日光の当たらない冷暗所で保管します。生酒であれば冷蔵庫に入れておきましょう。日本酒の正しい保存方法
日本酒は保存方法により、風味や香りが変質しやすい大変繊細なお酒です。賞味期限がないとはいえ、何も考えずに置いておくと、おいしさが半減してしまうこともあります。ここでは、以下のポイントから日本酒の正しい保存方法をご紹介します。- 温度
- 湿度
- 場所・日当たり
- 振動
- 臭い
①温度
日本酒は基本的に常温保存しましょう。なお、種類によっては冷蔵庫での保存が適する日本酒もあります。常温は、一般的には外気温を超えない程度の温度とされるものの、日本酒であれば15~20度程度が理想です。特に高温の環境で長期間保存すると、老香(ひねか)という劣化臭が生じることがあります。夏場は特に保管環境に注意しましょう。
また温度変化が激しい環境も、日本酒には適しません。できるだけ一定の温度を保つこともポイントです。
②湿度
高温だけでなく多湿を避けることも大切です。日本酒の場合、湿度の高い環境で保管すると、金属製のキャップや王冠にカビが生えたり、サビたりする原因になります。保管場所には温湿度計などを備えると分かりやすいでしょう。③場所・日当たり
日本酒は冷暗所での保管が基本です。特に直射日光に当たる場所で保管すると、紫外線の影響で日光臭という独特の臭いが発生してしまいます。なお、自然光だけでなく蛍光灯のような人工の光でも劣化を早めるため注意しましょう。薄暗い場所での保管が難しいときは、日本酒の瓶を新聞紙で包むなどして、できるだけ光が当たらないように工夫するのがポイントです。化粧箱に入れたままにすれば、手間もかからず、安定感も増してよいでしょう。
保存時の向きにも注意
なお、瓶の日本酒は保管時の向きにも注意しましょう。ワインなどは寝かせて保存するものが多いものの、日本酒は縦置き保存が基本です。縦置き保存をした方がよい理由は2つあります。1つは横向きにすると日本酒と空気が接する面積が増え酸化が早まるためです。もう1つは、日本酒が瓶の蓋に触れ続け、腐食につながる恐れがあるためです。
④振動
日本酒は振動によっても香りや味が変化します。人があまり通らないなど、家の中でも振動が少ない場所を選びましょう。特に冷蔵庫保存の場合、頻繁に開け閉めを繰り返すドアポケットなどに入れるのは適していません。⑤臭い
ここまでご紹介したとおり、日本酒は適切な方法で保管していても、劣化が進んでしまうことがあります。とはいえ、液色などに変化が生じていなければ、劣化しているかどうか分かりません。そこでポイントになるのが日本酒の臭いです。劣化した日本酒はこれまで説明した独特な臭いを発するため、目安となります。
老香 :漬物のたくあんのような臭い
日光臭:焦げ臭や傷んだ玉ねぎのような臭い
これらの臭いがするものは、品質が変化しているため飲まないようにしましょう。
日本酒の種類によっては、冷蔵庫での保管が好ましいことがある
一般的な日本酒は、温度がある程度一定に保てる冷暗所で常温保存して問題ありません。しかし生酒や大吟醸酒のように、特定の種類によっては常温でも日本酒の変質が早まる恐れがあります。種類別の保存場所や保存温度の目安は、以下のとおりです。
| 日本酒の種類 | 保存時の推奨温度 | 推奨保存場所 |
| 生酒 | 5~6度 | 冷蔵庫 |
| 生貯蔵酒 | 5~6度 | 冷蔵庫 |
| 大吟醸酒 | 10度程度 | 冷蔵庫 |
| 吟醸酒 | 10度程度 | 冷蔵庫 |
| 純米酒 | 常温 | 冷暗所 |
| 普通酒(特定名称酒以外) | 常温 | 冷暗所 |
生酒とは、上記の火入れの工程を一度も行っていない日本酒のことです。生貯蔵酒とは、出荷前に火入れの工程を1回だけ行った日本酒です。どちらも日本酒本来のフレッシュな味わいが楽しめる点が魅力であるものの、その分、品質の変化も早くなります。そのため、冷蔵庫での保管がおすすめです。
大吟醸酒は精米歩合が50%以下、吟醸酒は精米歩合60%以下で醸造アルコールを加えた日本酒のこと。
精米歩合とは、日本酒を作るときにどの程度玄米を磨いたかを表す割合で、数値が大きければ大きいほど米が残っており、フルーティーで華やかな香りと、甘みや旨味を感じられます。
精米歩合の大きい日本酒は、繊細な香りや味わいが魅力のため、これらの特徴を壊さないためにも冷蔵庫で保管した方がよいでしょう。
夏場であれば種類にかかわらず冷蔵庫保存も可
なお、長期間室内が高温になる夏場であれば、日本酒の種類にかかわらず冷蔵庫で保管しても問題ありません。エアコンでの温度管理も方法として考えられるものの、これでは手間やコストがかかってしまいます。年中室温が高い環境であったり夏場であったりするときは、冷蔵庫で縦置きにして日本酒を保管すれば程度の品質を保つことも可能です。
製造年月が古い日本酒はどのような「色・香り」になるか?
製造年月が古いなど、長期保存により品質が変化した日本酒は、色や香りなどに特有の変化があります。見た目は大丈夫そうに見えても、口にしたときに苦味や酸味を感じるものは、品質が変化しているため飲まないようにしましょう。それぞれ、特徴を解説します。【色】黄色や茶色に変化する
古い日本酒は、糖とアミノ酸の化学反応により、液色が黄色や茶色に変化することがあります。また、先述した火落菌の繁殖した日本酒は白濁する点が特徴です。色が変化しているときは品質も劣化しているため、飲むのは控えましょう。
【香り】ツンとした酸化臭がする
古い日本酒の香りに多い変化として、酢のようなツンとする臭いがあります。酸化による変化が原因なので飲んでも問題はないものの、おいしくはないためおすすめできません。他にも、日本酒とは異なる異臭を感じたときは、飲むのを控えて破棄しましょう。【味わい】酸味や苦味が生じる
長期保存していた日本酒は、熟成によりコクが生まれるなど良い変化が生じていることもあります。しかし実際に飲んでみて苦味や酸味などを感じるときは、酸化や変質が進んでいるものと判断できます。軽度であれば飲めるものの、風味を損なっているためおすすめはできません。
以上、紹介した色や香り、味わいの変化は製造年月の古い日本酒だけでなく、蓋を開けた後の日本酒でも急激に進行します。もし、開封後の日本酒で前回飲んだときとは異なる色・香り・味わいを感じたときは、別の用途で使うのもおすすめです。
古くなった日本酒の活用方法
開封してから少し経ったものや未開封でも製造年月から1年以上経過したものなど、そのまま飲むのが少し不安な日本酒は、料理や美容などに活用するのがおすすめです。料理に使う
日本酒を料理に使うと、以下のようなさまざまな効果が期待できます。- 肉や魚の臭みを消す
- 調味料を素材に染み込ませる
- 素材をやわらかくする
- 素材の旨味を引き立てる
- 料理の味わいをよくする
例えばご飯を炊くときに少量の日本酒を加えると、お米の甘みが増しおいしく仕上がります。やり方は米3合に対し、日本酒大さじ1~2杯程度を加え、炊飯器などで炊くだけです。日本酒の香りが気になるときは、小さじ1にするなど、適宜調整してください。
日本酒風呂に使う
日本酒に多く含まれるアミノ酸には、肌を保湿したりキメを整えたりなど、複数の美容効果があります。そのためコップ1杯程度の日本酒をお風呂に入れれば、全身の美容効果が期待できるでしょう。ただし、アルコールに弱い方やお子さんと一緒に入浴するときは控えるようにしましょう。
未開封なら買い取りに出すのもおすすめ
製造年月からある程度時間は経っているものの、未開封で保存状態の良い日本酒があるなら、買い取りに出すのもおすすめです。人気の銘柄は買取価格も上昇しているため、開封して使い切ってしまう前に査定出せば、思わぬ値段がつく可能性もあります。日本酒に賞味期限はないものの品質は変化するため注意しよう
日本酒やウイスキー、ブランデーなどのアルコール度数が高いお酒は、雑菌がほとんど繁殖しないため賞味期限や消費期限を定める必要はありません。とはいえ、日本酒のような繊細なお酒は、保管方法により風味や味わいに変化が生まれやすいのも事実です。製造年月の古いお酒が出てきたら、料理酒や日本酒風呂に活用して飲まない方法で利用してもよいでしょう。また人気の銘柄は買取市場でも高値になりやすいため、一度査定に出すのもおすすめの方法です。